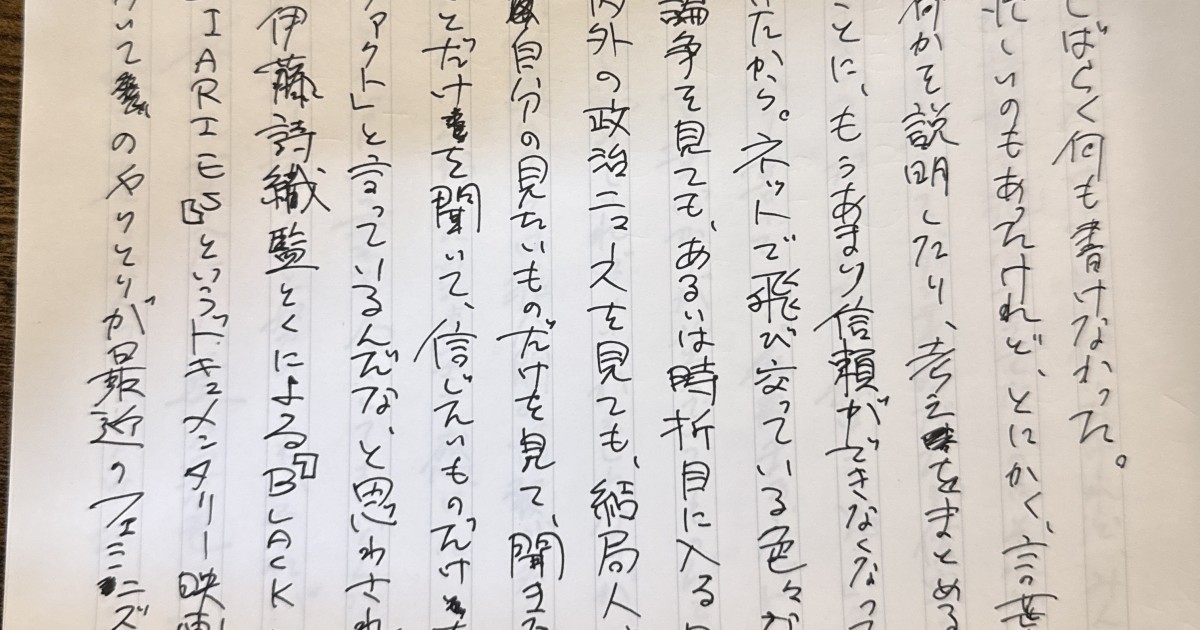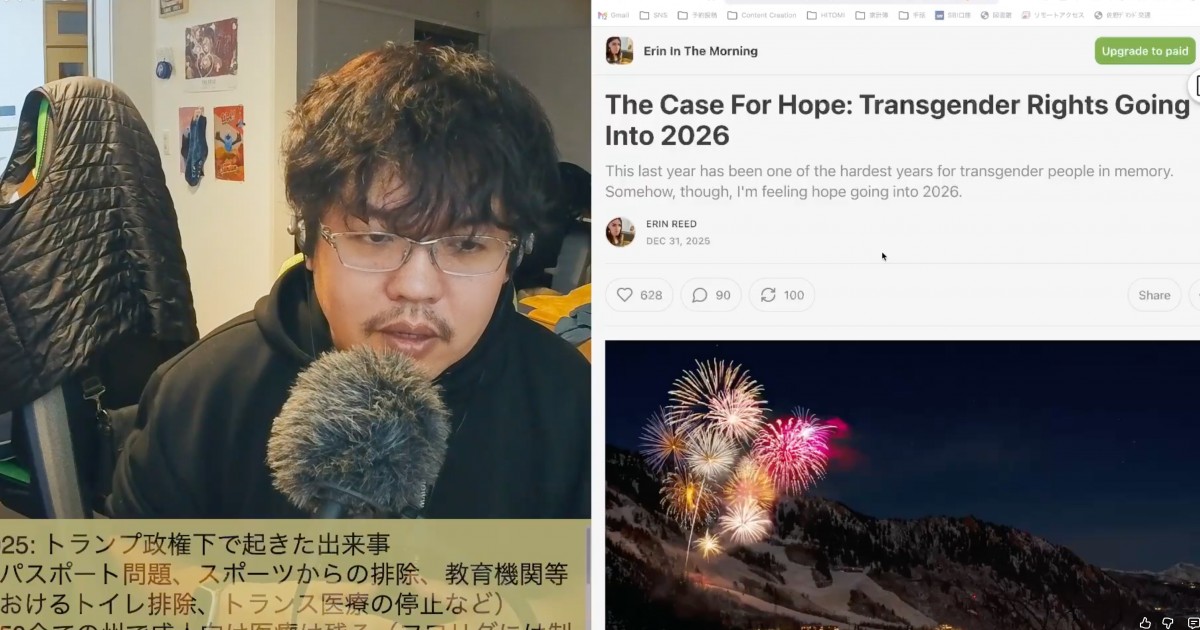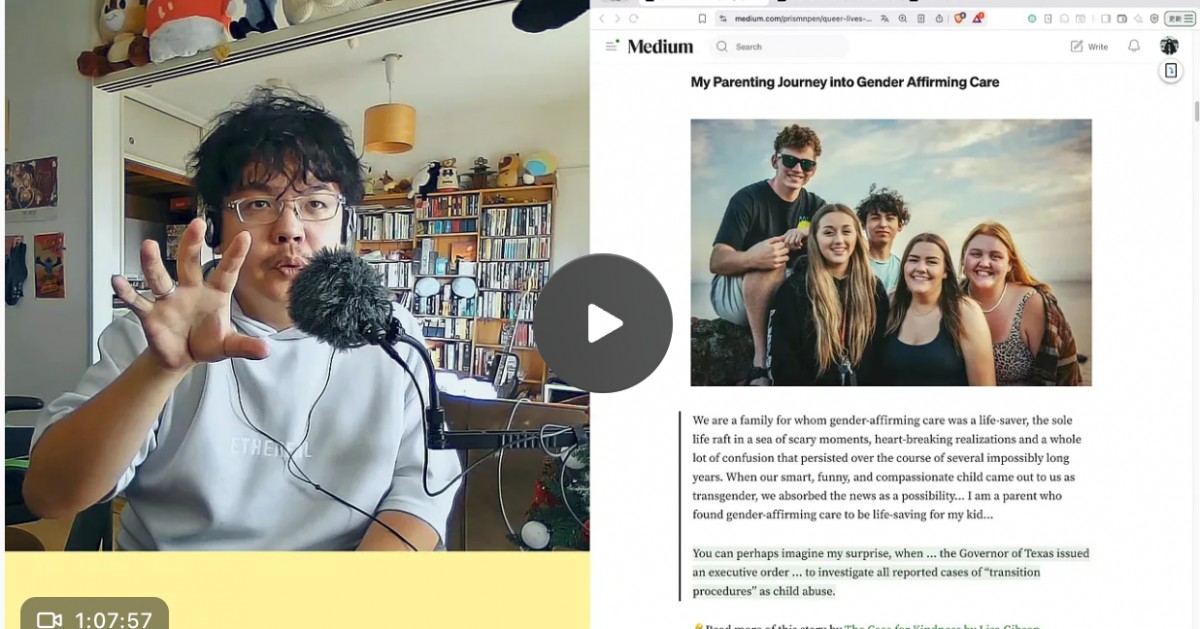私たちは、大騒ぎすることを自分たちに許さなければならない
(2022年3月2日にnoteに掲載したエッセイです。文中に「あらゆる国家の元首たちが、ロシアの行動を悪しきものと見做している」とした部分がありますが、2025年3月現在米国トランプ政権はあからさまに反ウクライナの姿勢を取っています。このエッセイでは自らの過去現在の残虐性を棚に上げて他者を叩く二枚舌を批判していますが、とうとう二枚舌を演じることすらやめて自らの残虐性に開き直り正当化する政権が米国に生まれてしまったことに果てしない悲しみを感じています。いずれにせよ、そのような時代の変化が起きたことを頭に入れて読み進めていただければと思います。)
祖母が死んだ。
その日はバレエの日だった。バレエの日というのは、週に一回、知り合いのバレエ教室の先生がやっている大人向けのストレッチ教室に通う日だ。10時に起きて、11時までにスタジオに行く。のそのそとベッドから這い出た10時半ごろ、母親から電話がかかってきた。
「ばあちゃんが起きないんだけど」
まだ寝巻きだった私は急いでコートを引っ掛け、同じマンションの母の家に走った。エレベーターを待っているのももどかしく、階段を駆け降りた。
ドアを開け祖母の部屋に行くと、眠っているかのような祖母がいた。肩を揺する。起きない。手を触ってみる。冷たい。
これまでも「もしかして死んでいるのでは」と思う瞬間というのは何度もあった。寝息が聞こえない夜とか、午後になっても部屋から出てこない時に、母と部屋を覗きに行って、呼吸を確認しては「紛らわしんだよ(笑)」と笑った。今回もそうだったらいいなと思っていた。
目に涙を溜めたまま、母と私は「ああ」「ああ」と繰り返した。「死んでるよね」と言う母の声が震えていた。「これは、死んでるねえ」——言葉に出すと、両目頭がギューっとなった。
状況を受け止めることができない私たちは、冷たい祖母を置き去りに、ひとまずリビングに戻った。母はパニックに陥っていた。
「どうしよう、どうしたらいいか分からない。まさかこんなことになるなんて」
「とにかく訪問ケアの人に電話してみよう」
私も冷静ではなかったけれど、二人ともパニクってしまうわけにはいかなかった。
いつも来てくれている訪問ケアの人が駆けつけてくれた。手を組ませ、祖母のお気に入りのハンカチでそれを固定してくれた。入れ歯を入れながら、「せっかく美人さんなんだから、ちゃんとしないとね」と祖母に優しく声をかけてくれた。

90歳当時、私の姉の披露宴にて(2016年)