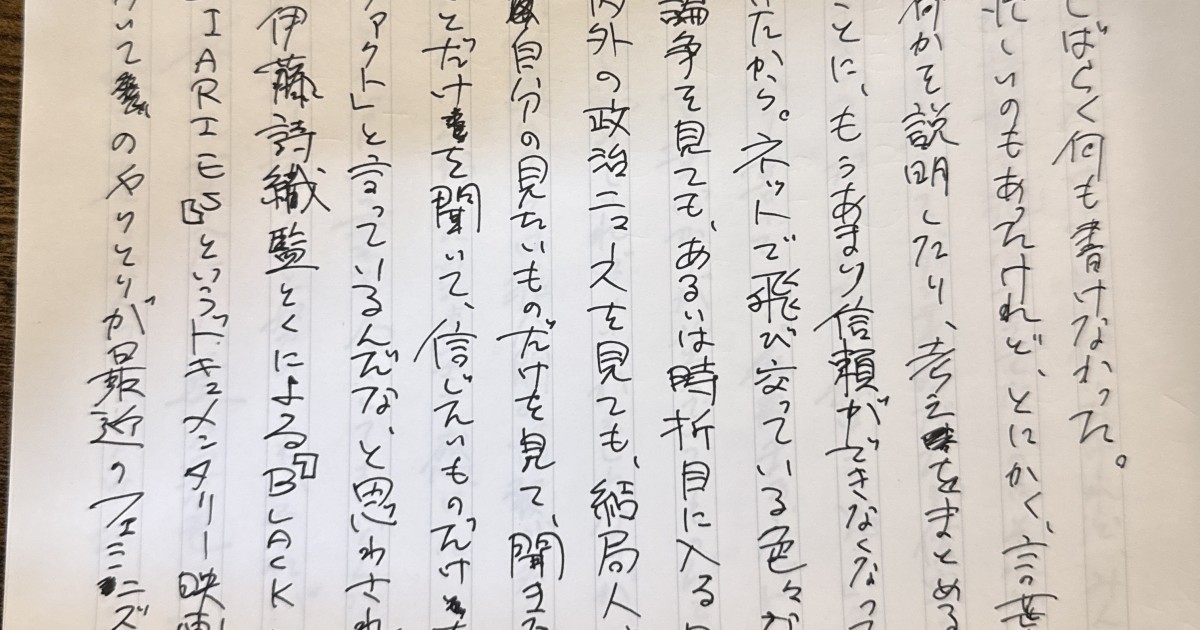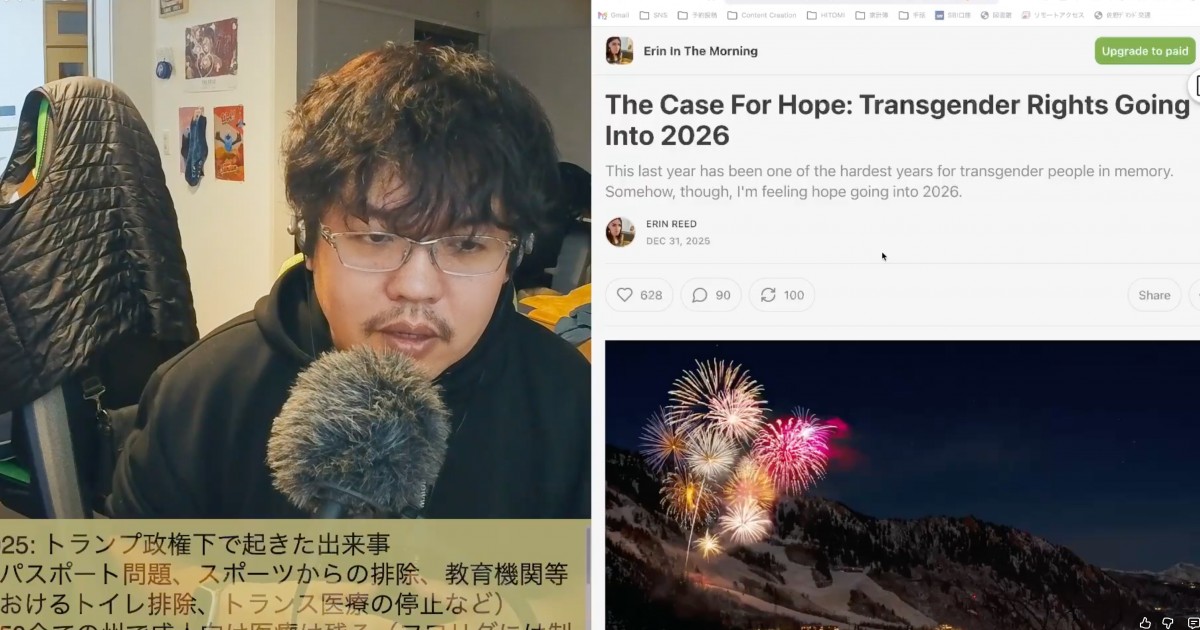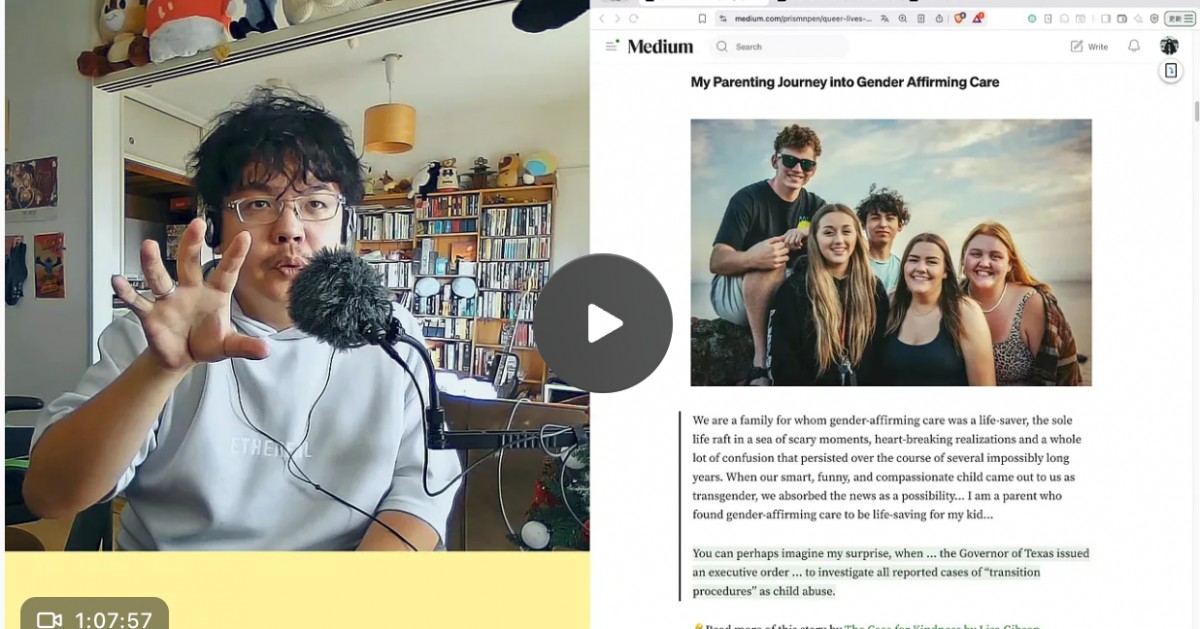もう麦茶なんて飲まない
おばあちゃんが死んだ、という話は前に書いた。まだ数年なのに、もう正確にあれが何年のことだったか忘れてしまった。たぶん二〇二二年だったと思う。二月だったことは間違いない。
今は二〇二五年の七月で、特段おばあちゃんのことを思い出すような時期ではない。けれど、死者というものはいつも思いがけないきっかけで僕たちの心を訪ねてくる。
夜中に調べ物をしていて喉が渇いたので、空のグラスをデスクからひょいと持ち上げ冷蔵庫に向かった。麦茶の入った大きな容れ物を傾けグラスに注ぐ。麦茶の香りがいつもより濃い。そういえば小さい頃、甘い麦茶をよく飲んでいたな。輪郭の淡い記憶が、香りとともに鼻から頭にかけて広がる。容れ物を戻し、冷蔵庫のドアを閉めながら一口飲むと、冷たさが舌、喉、食道を通り抜けてゆく。
昔飲んでいた甘い麦茶は、おばあちゃんが作った麦茶だった。当時も同じように冷蔵庫に大きな容れ物があって、そこにおばあちゃんが作った甘い麦茶が入れられていた。ふと、手に持っているこの麦茶も甘くしてみようかな、なんて思う。いや、冷たい麦茶に普通の砂糖を入れても混ざりが悪くてうまくいかないだろう、と思い直す。と同時に、あれ? じゃあどうやっておばあちゃんは麦茶を甘くしていたんだろう、と、キッチンとリビングの間あたりで立ち止まってしまった。
一度お湯で作った麦茶に砂糖を混ぜて、それから冷ましていたんだろうか。それとも冷たいものにも混ざりやすいタイプの砂糖があったりするのだろうか。思い返すと、おばあちゃんが大きな菜箸(さいばし)みたいなもので容れ物に入った麦茶をかき回していたのを見た記憶がある。あれは暖かい麦茶だったのだろうか、冷たい麦茶だったのだろうか。あれ、変だな、自分が菜箸でかき混ぜていた記憶も蘇ってきたぞ。でも、肝心の温度が思い出せない。
僕は口の達者な子どもであった。甘すぎるだとか、もっと甘くしてほしいだとか、ああだこうだ言った気もする。君が作ったのなら文句も思いきり言えたのに、もう麦茶なんて飲まないなんて言わないよ絶対、である。
ああ、もう聞けないんだねえ。
「あれってさあ、お湯で作ってたの?」
こんな簡単なことを、あんなにたくさんの時間を一緒に過ごしたのに、聞きそびれちゃったんだねえ。
すでに登録済みの方は こちら