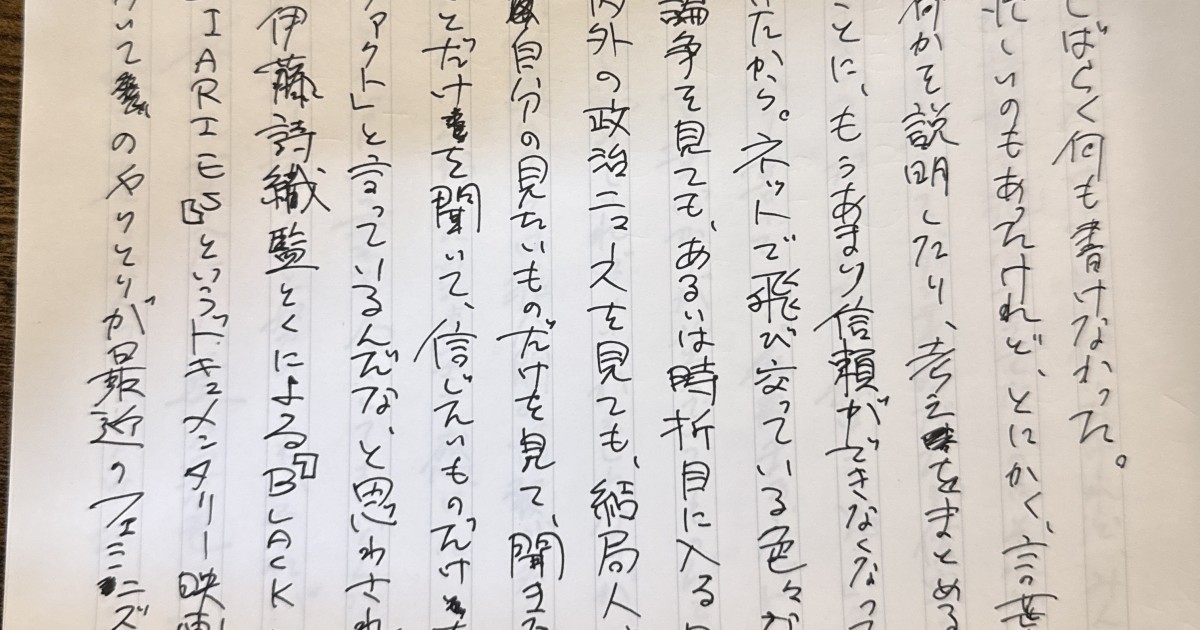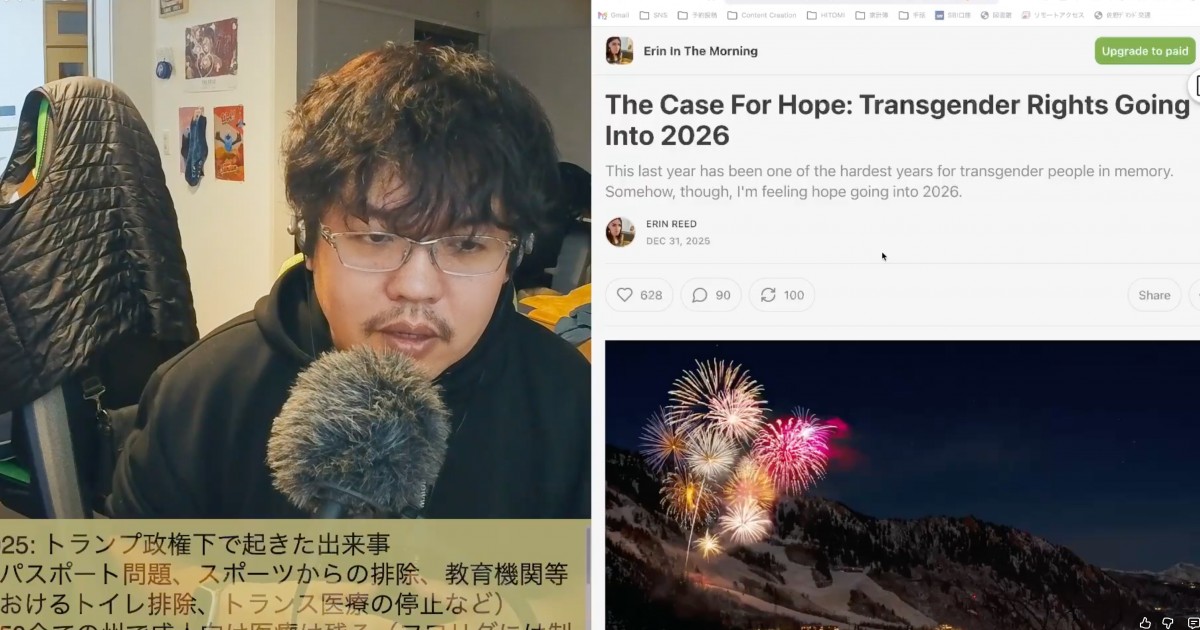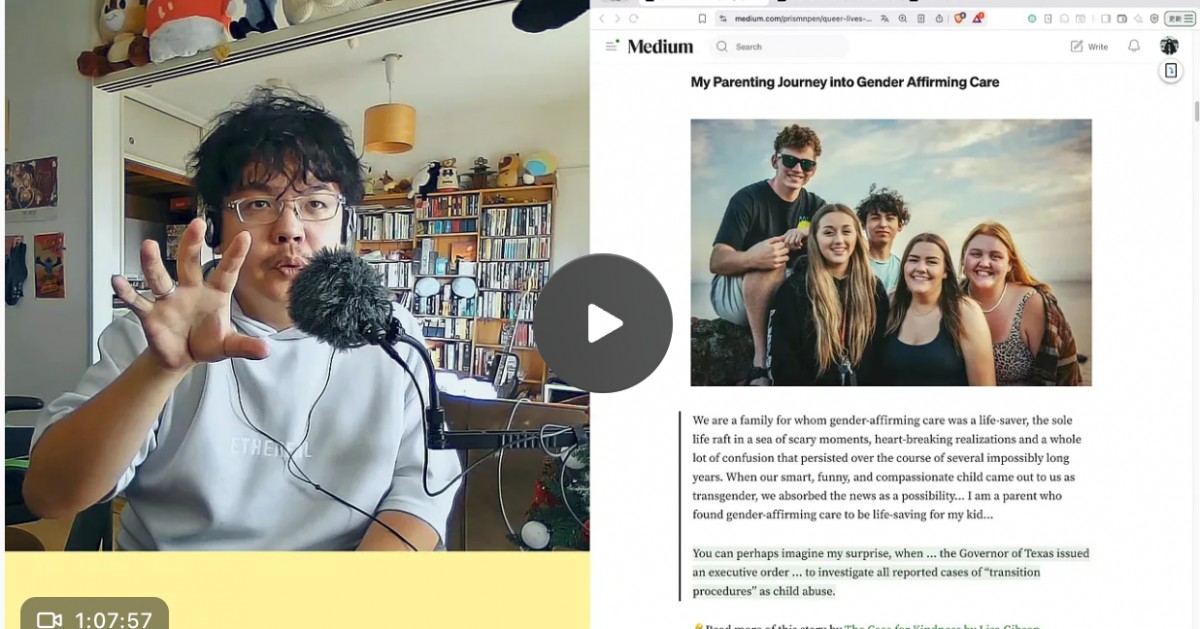大事なことを教えてくれた二人の移民
2005年の夏から2007年の春まで、私はカリフォルニア州サンフランシスコから BART(Bay Area Rapid Transit ベイエリア高速鉄道)で1時間半くらいのプレザント・ヒルという街に住んでいた。
そこではディアブロ・バレー・カレッジ大学に所属していた。同州の高校に編入したタイミングが受験時期にギリギリ間に合わなかったので、二年後に志望校に編入するつもりでこの二年制の大学に入ったのだった。
不本意だったとはいえ、この大学に入ったことで生まれた人間関係や、そこでの思い出は、とても大事なものとなった。ふと思い出してグーグル・ストリート・ビューを開く。

Google Street View
今は2023年なので、16年も経っているのだが、住んでいたアパートも、大学も、あまり変わっていなかった。懐かしいな、と思い、よく通っていた近所のスーパーまで足を——と言っても画面上で移動しただけだが——伸ばした。それが上の画像である。
そう、16年も経っているのだ。変わっているに決まっているのだ。アパートと大学が変わっていなかったのは本当にたまたまで、普通はこうして景色は変わるものなのだ。
だけど、とてもショックだった。
上の写真の左側、スペイン語の看板のある店は、メキシカン・レストランらしい。ここにはかつて、ギリシャ移民の老夫婦が営んでいたファストフード店があった。Gyros というケバブに似た料理を出していた。私はこの gyros が大好きだった。甘くないヨーグルトが少しスパイスの効いたソースと絡んで、週に1回、いや2回は食べていた気がする。
学生が多い街ではあるが、それでもあまり繁盛しているとは言えない店だった。この大学に通うのは大半が地元の若者や中高年で、その多くは少し離れた街に住処を持ち、仕事の合間に授業を受けにくる。大学の近くのアパートに住んで近辺をうろうろしているのは大半が遠くから来た外国人留学生で、かれらにとって gyros はあまり身近な食べ物ではなかった。
それをいいことに——と言ったら彼は心外だろうが——ここの店主はたいして長くもない営業時間の大半を店先のテラス席に座って過ごしていた。マイク真木のような、今でいうイケオジだった。横にサーフボードが立てかけられていても不思議ではない。いつしか私は、決まって羊肉の gyro を注文し、その親父が座っているテーブルに腰掛けるようになった。
私はこの親父が大好きで、そしておそらく親父も私のことが気に入っていた。