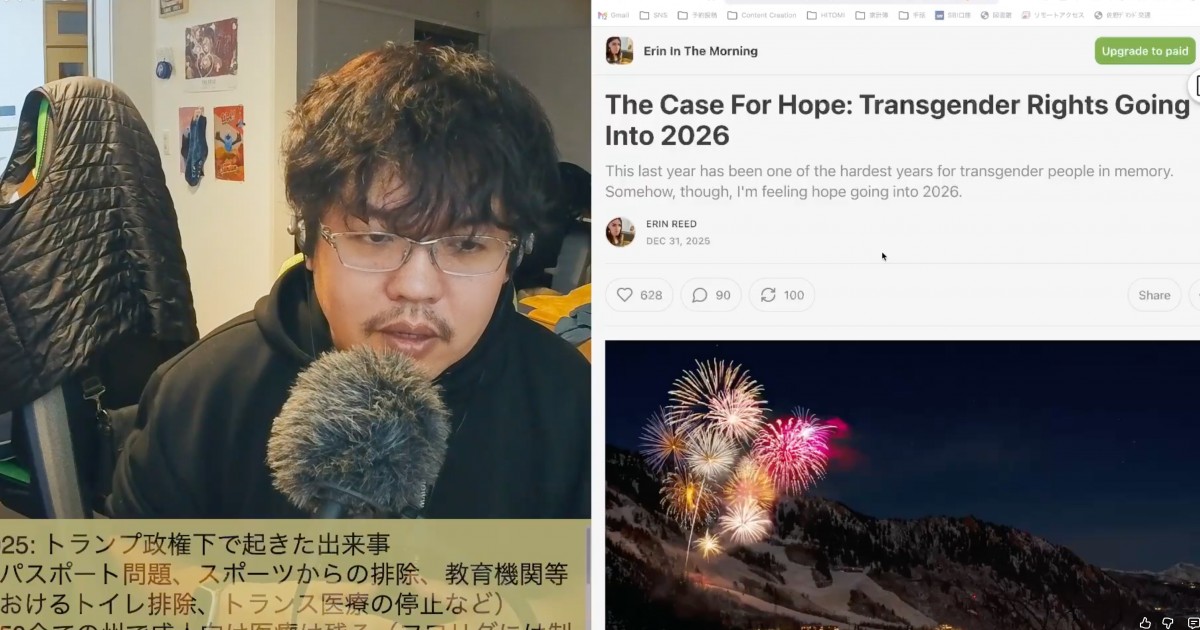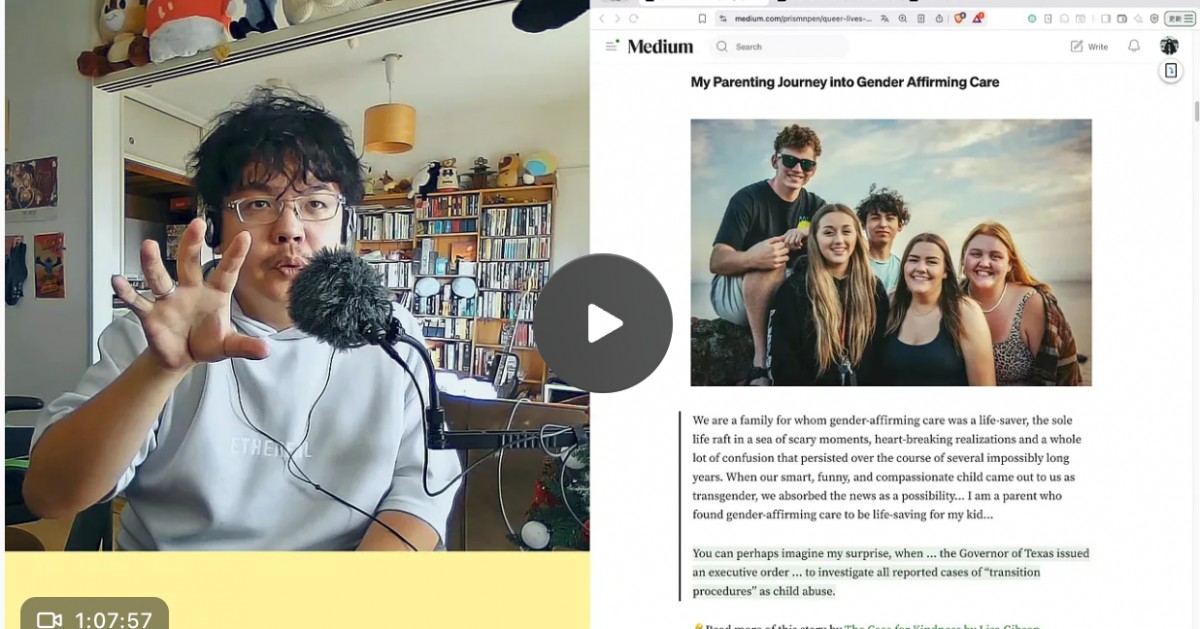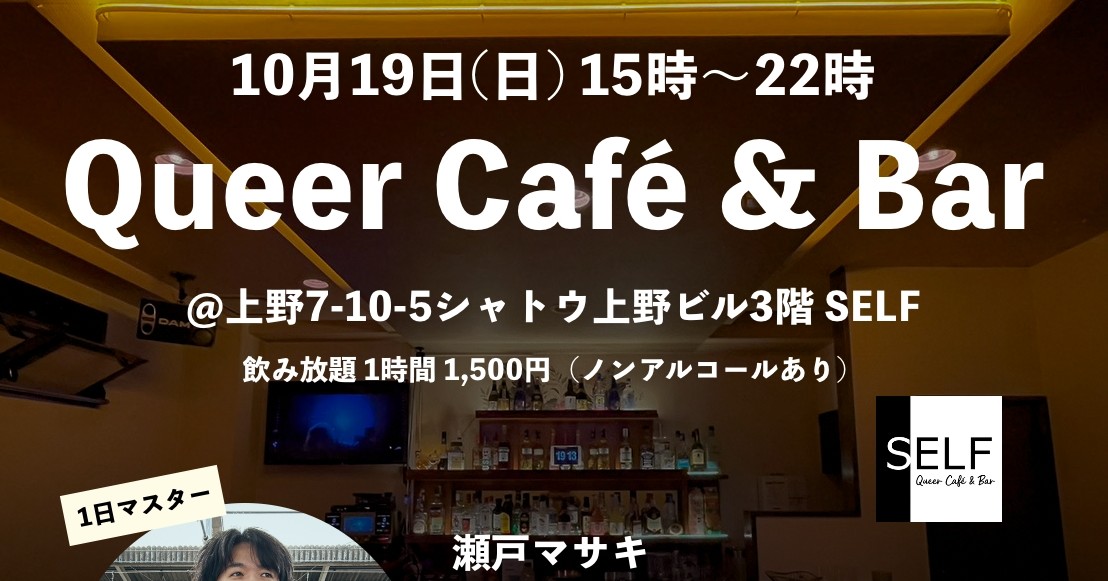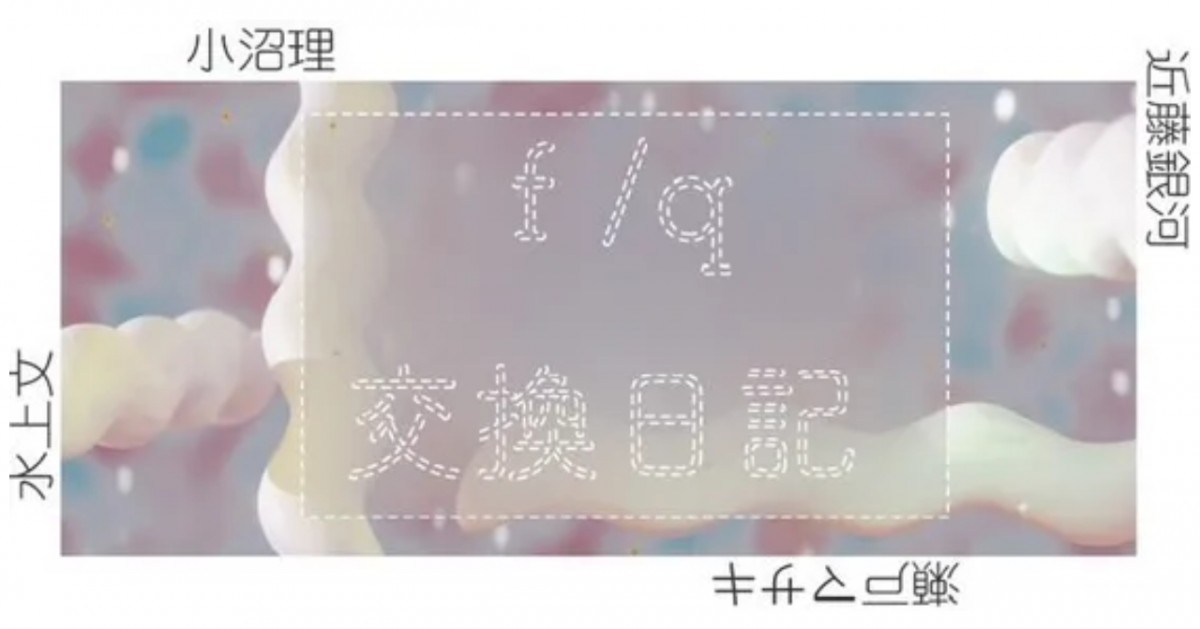ダニッシュにシロップを
あまり僕のことを知らない人に簡単に言っておくと、僕は十七のときに英語圏に引っ越した。二〇〇三年のことで、その後二〇一一年に日本に戻るまであちらこちらを行ったり来たりして過ごした。そう考えるとこれまで約四十年の人生でたったの八年、実際には年度のずれや日本の大学に通った期間もあったのでもっと短い期間、だいたい五年くらいしか英語圏にいなかったのかと自分でも驚くが、それでも一七歳からの八年間を行ったり来たりして過ごしたのは濃密ではあった。
日本語よりも英語が得意になる、ということはなかった。英語でのやりとりに困難を感じることはないし、突然明日から英語圏で生活することになっても、まあ生業(なりわい)は見つかるだろうし、住むところも得て、近所に知り合いなんかもできて、貧乏なりではあるがそこそこ楽しく生きていけるだろう、と思えるくらいには英語が身についている。
ただし語彙だけは別で、いまだにザ・ニューヨーカーのような小洒落(こじゃれ)た出版物を読む時は一記事につき少なくとも十回は単語の意味を確認している。書くときも似たようなもので、真面目な文章を書いてるとき、確かこんな言葉があったはずだと感覚で打ち出した言葉に突然自信がなくなり、ブラウザに貼り付けて確認すると、はたして実際にそういう言葉が存在することを知って安堵(あんど)する、ということがしょっちゅうある。
一方で、では典型的に多くの知識を仕入れる時期である十代後半から二十代前半の時期に日本にいなかったことがマイナスに働いている側面はあるのかというと、実はある。一つは、当時流行った音楽やドラマに馴染みがないということ、特にCMの知識が完全に抜けていることである。そしてもう一つのマイナスの側面は今から話すことであり、実は現時点で僕はそれをうまくまとめて言語化できていない。抽象的な話をするよりも、具体例を出した方が早いだろう。
先日友人と通話していたときに、どんな流れだったか、ミュージシャンのSIRUPの話になった。僕はこのミュージシャンの名前を音声で聞いたことがなかったし、口に出したこともなかった。社会正義の観点からの発言が目立つ人なので、僕の知り合いにもファンだったり彼を追っている人は少なくない。だからインスタグラムにせよXにせよ、あらゆるところで彼の名を目にすることは多かった。でも、それをどう発音するのかは知らなかった。
なので僕は「シロップ」と言った。ドロっとした甘いあれと同じ読み方である。ドロっとした甘いあれは英語でSYRUPと綴(つづ)る。かつての日本の人はそれを「シロップ」と表記することにしたのだ。